Paul Yamazaki氏は、1970年からブックショップ「シティライツ・ブックセラーズ」の主任/チーフバイヤーとして活躍している。 また、文学雑誌協議会、Small Press Distribution、Kearny Street Workshopなどの文学・芸術団体の役員を務めている。 また、GrantaのBest of Young American Novelists 2の審査員を務め、2014年のDSC Prize for South Asian Literatureの審査員も務めている。 リトケイク・バーバリーコースト賞受賞。
インタビュー抜粋 :-
Q1) シティライツはいつ始まり、どのようにしてそのような機関になったのですか?

Paul : City Lights Booksは1953年に設立され、ちょうど67年目を迎えたところですね。 アメリカの著名な詩人であるローレンス・ファーリンゲッティが設立したものです。 1955年に出版部門を設立し、最初に出版した5冊の本のうちの1冊がアレン・ギンズバーグの『吠える』と『その他の詩』で、これが私たちの世界的な地位を確立するきっかけとなりました。 ローレンスはギンズバーグの『吠える』の最初の公開朗読会に出席し、その夜、彼に電報を送りました。「これは驚くべき詩の声の始まりだ」と言い、原稿(原本)をいつ入手できるかと尋ねたのです。 ローレンスは、この作品が物議を醸すことを承知で、それでも一歩も引かなかった。 出版に伴い、いわゆる猥褻図書を販売したとして、店長とともに逮捕されるという苦境に立たされた。

City Lightsからアレン・ギンズバーグの詩「吠える」が出版され、ボヘミアンと文学者が集まる場となった。
ブックショップは、社会学を教えるために1940年代にニューヨークからサンフランシスコに移住したピーター・D・マーティンの啓示でした。 彼は以前、1952年にチャップリンの映画にちなんで「シティ・ライツ」を雑誌のタイトルとして使い、フィリップ・ラマンティア、ポーリン・カエル、ジャック・スパイサー、ロバート・ダンカン、そしてファーリンゲッティ自身といったベイエリアの主要作家の初期の作品を「ローレンス・ファーリング」として出版していました。 1年後、マーティンはその名前を利用して、アメリカ初のオールペーパーバックの書店を設立します。当時、それは大胆なアイデアや思想に思えました。

1953年に、ファーリンゲッティがアルティグ・ビルを散歩していると、表のほうに「ポケットブックショップ」の看板を掲げているマーティンを見かけました。 彼はマーティンの雑誌『シティライツ』の寄稿者であることを知り、自分がずっと本屋を経営したいと思っていたことを打ち明けた。 しばらくして、彼はマーティンと共同経営することに同意した。 出資金は各人500ドルだった。

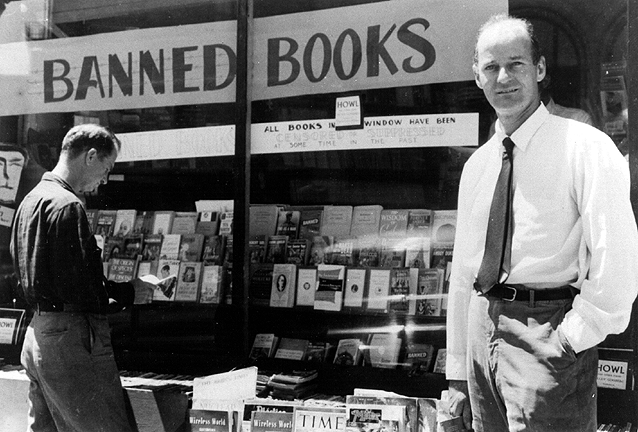
Q2) City Lightsは注目すべきランドマーク、ビート世代への生きた賛辞、サンフランシスコ文学界にとって居心地のよい空間となっていますが、これはどのような理由からでしょう? これらは、店の本のキュレーションやセレクションにどのように影響しているのでしょうか?

Paul : ローレンス・ファーリンゲッティは常にシティライツを可能性の灯台、そして可能な未来と展望の長いスカイラインについて考えるための避難場所と考えていました。 彼は常に、シティライツは、ブラウザや読者がラックを吟味し、数冊の本を選び、自分のペースで読むことができる、生き生きとした静寂とエネルギッシュな静寂の場所でなければならないと考えてきました。 この抵抗と可能性の広い土手の間に、反対する創造的な心を駆り立てる作品を取り入れるというシティライツの学芸員としての使命があります。

Q3) ブックセラーであることの最大の魅力は何ですか?

Paul : アメリカの独立系書店は、第二次世界大戦後の国際主義にその基礎があります。 サンフランシスコのベイエリアのシティライツ、ケプラーズ、コディーズ、ニューヨークの8番街ブックショップは、第二次世界大戦後の10年間に設立されました。 8thストリート・ブックショップとシティライツは、ビートと呼ばれる革命的な詩人や芸術家の出版社でもあった。 ロイ・ケプラーは、第二次世界大戦中、アメリカ政府によって投獄された保守的な戦争抵抗者である。 戦後、ケプラーはサンフランシスコのベイエリアにおいて、社会的、政治的に重要な人物となった。 1960年代から1970年代にかけて登場した書店の多くは、ラディカルストアの精神に影響を受けている。 過去数十年の間に、毎年出版される本の数は驚異的に増加した。 独立系書店は、適切な本を適切な読者の手に届けることができる。 読者は私たちが提供するこのサービスに感謝しています。

Q4) お店とはどのようにお付き合いされましたか?

Paul : 政治・社会活動をしていて、半年ほど収監されたことがあります。 1ヶ月早く出所するためには、雇ってくれる人が必要でした。 ある仲間が書店の社長のところに行き、私のことを教えてくれたんだ。

Q5) 主任バイヤーとして、どのように本を選んでいるか読者に少し教えていただけますか?

Paul : 書店の本を選ぶことやキュレーションはそれ自体が専門性や技術であり、私が50年間ビジネスをしてきた中で多くのことが変化・発展しましたが、読書、興味、会話という書物販売の基本は変わりません。 それが私の仕事の核心です。 さらに、「シティライツの本をどのように選んでいるのか」という質問に対しては、「できるだけ多くの本を読み、全国の独立系書店、大小の出版社の編集者、出版社の営業担当者やエージェント、シティライツの同僚と会話をして、答えを探っています」と答えます。 ここで、どんな本を読むか、どんな本を棚に並べるか、という議論は、まずスタッフから始まります。

編集者と継続的に話し合い、コミュニケーションをとることも重要な点である。 私たちは編集者と会話を交わし、新しい著者の著作やその本について調べることで、私たちのスタッフがいち早く読者になることを許可しています。
Q6) 書店はどの社会、地域でも文化的なプラットフォームです。 書店は、読書家にとって、自宅から離れた場所、あるいは現実からの逃避先として機能しており、そこには明らかに何らかの帰属意識があります。 人々、特に読者にとっては、どこか聖域のようなものなのです。 あなたはこれに同意しますか
?